
「あなたがたは世の光である」(マタイによる福音書 5章14節)
イエス様は主に従う人たちが世の光であると言われました。
それは、地の塩と同じように、世の光も、この社会の中にあって働くということです。
その働きは、自分の気に入る人のためというよりもむしろ、そういう偏見を超えて、暗闇の中にいる人々のため、悩みに沈んでいる人のためなのです。
パレスチナ地方の庶民の家は、直径50センチ程度の丸い窓がある以外は、外からの光を採り入れる場所がありませんでした。そこで、部屋の中を照らすために、ランプに火をともして燭台の上に置きました。当時はマッチがありませんでしたから、火を起こすのは一仕事でした。
ですからランプに一度火を付けたら、それをなるべく消さないようにしていました。
そこで、外出するときは、帰宅するまで安全に灯がともっているために、燭台から外して升の下に置くようにしていました。そういうわけで、ともし火をともして升の下に置くのは外出時のことです。
人間が家の中にいるときには、燭台の上に置かないと意味がないのです。
どこに何がおいてあるかがわかって、ものにつまずくことなく歩くことができるようにするためです。世の光とは、そういう働きをするものです。
神様が私たちに与えられている世の光としての働きとは、今の暗い世の中をどのように歩んで
いったらよいのかを、人々に示すことです。

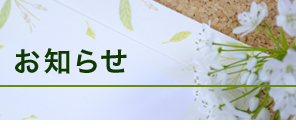
Comments are closed.